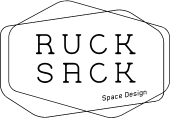9月に陸前高田へ初めて訪れたときから3か月。
被災した方々から伺うここで起こったこと、津波が残した巨大な傷跡に圧倒されっぱなしだった。
現実に起こったことや目の前にあることをうまく受け入れられず、私達は混乱していた。
それでも早く同じ場所へ再び来たいという思いがあった。
それは9月に炊き出しをした後、急きょ近くの仮設住宅に料理と食材を届けに行ったことがきっかけだった。
持っていった食材では数が足りず、集まった方をがっかりさせてしまうことがあったのだ。
レトルト食中心の暮らしを続けている中においては、温かい手料理は久しぶりという方も多く、
その時のがっかりとした姿は脳裏に焼き付いて離れなかった。
炊き出しのメニューはカムチャンサムギョクサルどんぶり(醤油漬け甘辛豚バラ丼)、トックスープ(韓国のお雑煮)、キムチ。
前日から150世帯・450人分の下ごしらえを整え、調理器具やガスボンベなどを3台の車に分けて積み込んだ。
今回は敷地内にある集会所から電源と水を使えることになり、炊飯器を8台持参して手間の省力化を図ることができた。
また、食器やおはしは各々で持参してもらうことで、私達はおいしい食事をつくることに専念した。
皆さんが手に持つ食器は様々で、夜帰宅する家族の分をと片手鍋を持ってくる方もおられた。
食材は余裕を見て用意していたのだが、残らず配り終えることができた。
9月に料理を渡せずにがっかりさせてしまった方に再会することができ、今回はちゃんと手渡しすることができた。
10日の朝の気温は-3°。
雪は降っていないが刺すような寒さ。
仮設住宅の断熱工事が急ピッチで進んでおり、敷地内にはエアコン設置業者の姿も見受けられた。
今回はこれから厳しくなる冬に備え、ご厚意で集まった防寒着や手袋・毛布・マフラー等を持ち込んだ。
楽しく選べるようにハンガーにかけ、気に入ったものを持ち帰ってもらった。
しかしまだまだ防寒着や毛布は不足しているそうで、毛布はすぐになくなった。
部屋の断熱が不十分なのか、部屋を暖めると結露がひどいという。
新年を温かく迎えるにはまだまだ足りないものがたくさんあるようだ。
仮設住宅は市街地近くの丘の上にある。
市街地には何も残っていないため、近くには買い物に行く場所や娯楽施設がない。
まとまった買い物をする際は一関あたりまで足を延ばすしかないそうだ。
ここでの暮らしは「仮設」の箱に住むという内的不自由さと、
施設が欠落した街の中で活動しなければならないという外的不自由さとの板挟み状態。
引きこもり勝ちになり、鬱状態に陥る方も多い。
そのような状況の中では炊き出しやイベントごとが重要な役割を果たす。
部屋の外に出るきっかけとなり、人と会話する機会を生み出す。
バラバラになってしまったコミュニティの再生。
それを加速させる作用があると、現地窓口になっていただいた金氏は言う。
炊き出しを終え帰路につく際、数人の方が出口で待っていてくれた。
そして笑顔で見送ってくれた。
大切につくった自家製のたくあんをお礼にと頂いた。
家族を失い大切なものを失ってなお他人のことを気遣う人の強さとやさしさ。
一日でも早く安心して暮らせるよう心から願う。
気仙沼
一関から陸前高田に向かう際、気仙沼の市街地に立ち寄る。
巨大な鉄でできた船が街の真ん中に横たわっている。
紙屑のようになった自動車が船底に敷かれている。
被害があまりにも甚大なため、一見するとあまり変化ががないように見えるのだが、
道路の整備は進み、9月に見た状況に比べると瓦礫の撤去はかなり進んでいるように見受けられた。
復興には長い時間がかかるだろう。
そして多くの痛みを伴うだろう。
もくもくと瓦礫を撤去している作業を見ていると必ず道は開けてくると感じる。
これを乗り越えた時、日本を牽引する新しい街になることを期待してやまない
参加
- 丁仁英
- 西村祥子
- 三部由夏子
- 三苫健次郎
- 菅野知良
- 小林亜希子
- 川崎真琴
- 草島智道
- 上村昭則
- 田中博亮
協力
- 櫻井雅子
- 長岡真里
- 上和田久美子
- 大井美穂子
- 簗瀬真由子
- 福間祥乃
- 金田みゆき
- 原田往子
- maturense
- 管隆志
- 岡本美都夫
- 古賀正章
- 高須里美
- 吉村奈穂
- あそび心研究所
- 大人なのに無茶する会
- 陸前高田ボランティアセンター
- 世田谷区立深沢児童館
- RUCKSACK SPACE DESIGN
震災から半年。
被災された方々にとってどのような時間だっただろうか。
私達はメディアを通して経過を見聞きしているものの、時間と共にリアリティは希薄になり記憶は曖昧になりつつある。
避難生活者は9月1日現在で3万8000人。5月時点での12万人という数値に比べると大幅に改善されたように見える。
しかしそこには仮設住宅生活者4万5000人は含まれていない。
プレファブのボックスに移動した時点で被災者としてカウントされないのである。
実際の生活環境はどのようなものだろうか。
失った家族や友人、消え去った家、大切にしていたもの全て。
損なわれた精神的支柱と、現実社会で直面する諸問題との板挟みから脱するには、それなりの時間と手厚い保護が必要。
陸前高田ボランティアセンターには400名近くのボランティアが活動を続けているが、全く手が回らない状態が続いている。
これまで私達は福島の避難所で炊き出しを行ってきたが、今回は少し状況が異なる。
開催地は岩手県にある陸前高田市。
津波によって壊滅的な被害を受けた街である。
「避難所」ではなく「被災地」に足を踏み入れるのはこれが初めてであり、開催地である河川敷には屋根も電気・水道もない。
往復1100kmの移動に耐える食材の衛生管理、水を含む全ての材料・機材の持ち込みが必要となった。
今回の炊き出しのイベントは支援団体「縁起屋」斎藤亮氏の呼びかけ「希望の気球」をお手伝いする形での参加である。
彼は3.11から間もない頃このプロジェクトをスタートさせた。
文字通り手さぐりで地元と行政との協議を重ねようやく実現に至ったのだ。
会場には早朝にもかかわらず多くの方が足を運び、正午には延べ400人が気球に乗って景色を楽しんだ。
巨大な気球は時折バーナーから轟音を発し、ゆっくりと空に浮かぶ。
しばし日常を忘れさせ、乗った人を笑顔にする不思議な力をもった乗り物。
炊き出しのメニューはサムギョクサルどんぶり、カレーライス、キムチ、パウンドケーキ。
前日からメンバー総出で300人分の下ごしらえを整え、加熱・炊飯は現地で行う形をとった。
普段食事はレトルト食品がほとんどという方が多く、「手作りの料理は久しぶり」と喜んで頂けたようだ。
イベント終了後、カレーと持参した食材や菓子と共にトラックの荷台に乗り、第一中学校にある仮設住宅に届けに行く。
ここでの食材不足は深刻で、持参した食材はすぐに底をついてしまった。
食材が行きわたらず、がっかりとした表情で仮設住宅に戻る姿は、避難生活の過酷さを感じさせる。
気仙沼
東京に帰る際、港と気仙沼に立ち寄る。
目に入ってくるのは紙くずのようになった車、砕けた電柱、スケルトンだけの建物群、泥まみれの畳の山。
3.11、この中に多くの人が巻き込まれて命を落とした。
瓦礫は当時の壮絶な状況をかろうじて今に伝える数少ない手がかりである。
復興が進むにつれ、間もなく瓦礫は処分され、破壊された建造物も解体されるであろう。
震災の傷跡は消え、少しづづ人々の記憶からも生々しさは薄れていく。
私達は震災の姿を目に焼き付け、長い帰路についた。
参加
- 丁仁英
- 江馬優子
- 岡本美都夫
- 大澤沙絵子
- 西村祥子
- 三苫優仁
- 三苫健次郎
協力
- 江馬則子
- 三部由夏子
- 櫻井雅子
- 長岡真里
- 吉原淳子
- 上和田久美子
- 今成晃子
- 大井美穂子
- 尾澤律子
- 飯久保京子
- 石川ひろみ
- 黒崎みどり
- 玉川慶姫
- 田邊晋代
- 千葉知子
- 山下文子
- 安井能理子
- 藤田奈緒美
- 吉田佳寿子
- 奈良友里
- 簗瀬真由子
- 縁起屋
- 大人なのに無茶する会
- 陸前高田ボランティアセンター
- 世田谷区立深沢児童館
- RUCKSACK SPACE DESIGN
震災から2か月半。
避難生活をされている方はどのくらいいるのだろうか。
集計によると全国で約12万人、そのうち福島に留まって避難生活をされているのは約9万人。
多くの方が見知らぬ場所へ行くより地元に留まることを望んでいることになる。
支援に向かった「パルセ飯坂」は福島市内にあり、避難所に指定された公共施設。
そこで避難生活をされている方には2次、3次避難先という方も多く人数は常に流動的である。
ここでは体育館のような大部屋を仕切る形ではなく、小部屋を数家族ごとにシェアしており、
仮設住宅的なつくりになっている。
5月28日現在、80名程の避難生活者と市の職員、ボランティアの方々が滞在されており、
出入り口では必ず消毒薬で手を洗うなどして衛生管理に気を配って生活している。
当日、ボランティアはマッサージ師、風船アーティストが希望者に持前の「技」を提供しており、
その中で我々は韓国料理の昼食を提供した。
前回スイーツまで用意出来なかったが、今回は手作りパウンドケーキもあり大変好評であった。
また吉本興業のタレントさんにお手伝い頂き心温まるイベントとなった。
ぺんぎんナッツさんブログ→ http://inano.laff.jp/blog/2011/05/post-d1c1.html
命をつなぐための状況を脱し、今は社会復帰を目指す避難生活に移行しつつある。
避難所から学校や仕事に向かう方も増えているが、
お年寄りや持病を持っている方の復帰は住環境が整わないかぎり難しい。
今後は避難生活にも多用化が進み、ボランティアに求められる要素も変わってゆくだろう。
とはいえまだ復帰への動きは始まったばかり。
労力、物資、技術、金銭、カウンセリング等あらゆる支援が必要なのはしばらくは変わらない。
参加メンバーの「おいしい食事を届けたい!」という強い思いから始まったこの活動。
それに対呼するように支援の輪も広がっている。
参加
- 丁仁英
- 三部由夏子
- 櫻井雅子
- 長岡真里
- 吉原淳子
- 江馬則子
- 上和田久美子
- 上和田理子
- 三苫優仁
- 三苫健次郎
協力
- 松井佐代子
- 黒崎みどり
- パルセ飯坂
- 東日本大震災ボランティアバックアップせンター
- ハートネットふくしま
- パルセ飯坂
- 世田谷区立深沢児童館
- よしもと興業
- 黒田豊
- 今井万博
- 渡部裕美
- 渡部美保
- 永田孝之
- 蔵並裕樹
- 加茂建
- プントデザイン
- 鴨邦高
- エアルームプロダクツ
- 高下達広
- 河野光輝
- 杉浦重治
- 山口晃央
- 有吉徳洋
- 金石浩一
- 南場立志
- 益田英法
- 伊藤端史
- 木村光博
- 小野正美
- 小野節子
- RUCKSACK SPACE DESIGN
東京から福島県まで車で3時間。
この距離は決して「遠いところ」ではない。
普段メディアを通して見る震災を、隣でおきていることとして意識している人がどれだけいるだろう。
支援に向かった郡山養護学校は福島第一原発より40㎞程西に位置している。
そこで避難生活をされている方のほとんどは原発の近くに住んでいた方たち。
4月24日現在、84名の避難生活者、職員、ボランティア、自衛隊の方々が滞在されていた。
我々はそこで韓国料理の昼食提供と子供たちに簡単な折紙ワークショップをさせて頂いた。
料理は野菜を中心としたビビンパとトックスープ。野菜のおかわりをされる方が多かった。
出番を終え引き上げる際、多くの方に感謝の言葉をかけて頂き元気を頂いた。
言葉、物資、まなざし、温もり、笑顔、何でもいい。
手渡ししてみて初めてわかることがある。
互いの心情が心に響く瞬間があり、痛みが少し伝わってくる。
他者との交流は希望をイメージする力となり、我々は近くの出来事としてリアリティを持つ。
原発に「福島」という名称があることで、福島全体が汚染されているように誤解されている。
だが決してそうではない。
福島は生きているし、これからも人々の暮らしは続く。
この美しい土地は簡単には損なわれない。
「このことを全国の人に伝えてほしい」と皆さんから強いメッセージを受け取り帰路についた。
参加
- 丁仁英
- 三部由夏子
- 櫻井雅子
- 長岡真里
- 吉原淳子
- 上和田久美子
- 小野正美
- 小野節子
- 三苫優仁
- 三苫健次郎
協力
- 松井佐代子
- 笹の川酒造 山口恭司専務ご夫妻
- 東日本大震災ボランティアバックアップセンター
- ハートネットふくしま
- 福島県立郡山養護学校
- 世田谷区立深沢児童館
- RUCKSACK SPACE DESIGN
避難生活と建築
過酷な避難生活を支える者がいる。
地域の職員、自衛隊、様々なボランティア 等々
そして建築もその一つ。
郡山養護学校は渡部和生氏が設計し1999年に竣工した美しい建築空間である。
過酷な避難生活の舞台となる体育館は明るい光に満たされている。
そして天井を見れば美しい空が見える。
建築が救いを与える瞬間がある。
美しい光に満ちた空間は、さりげなく希望や活力を人に与え続けている。